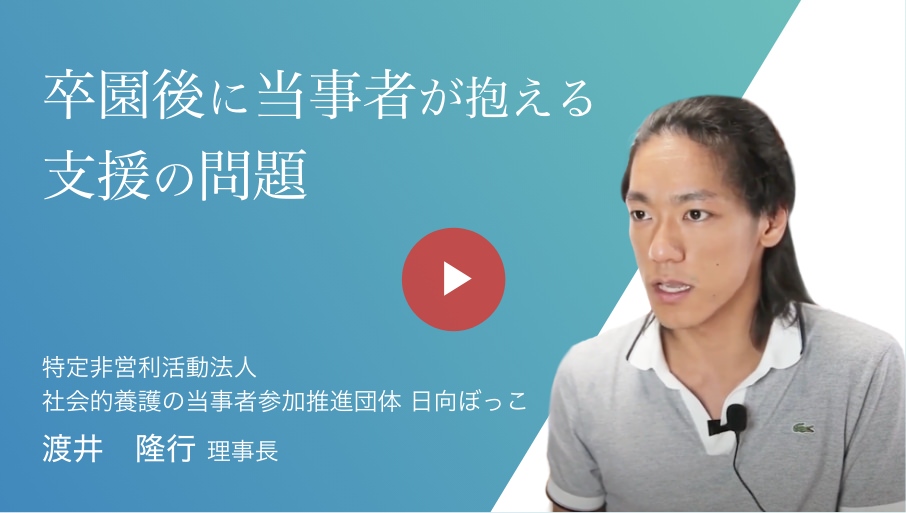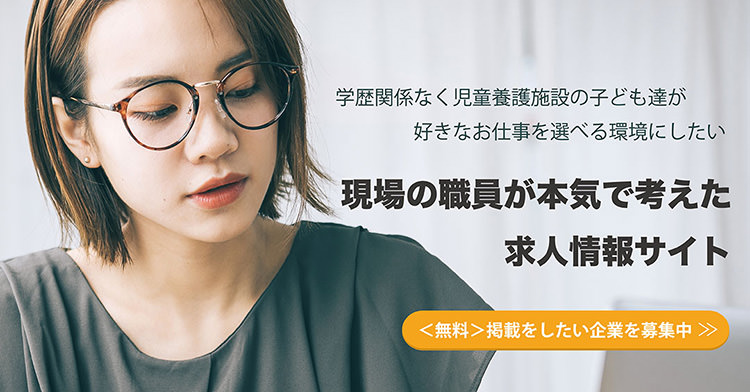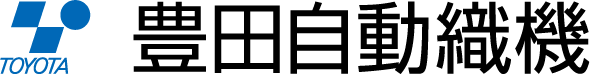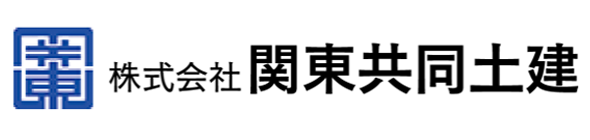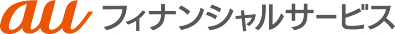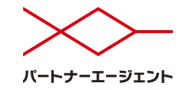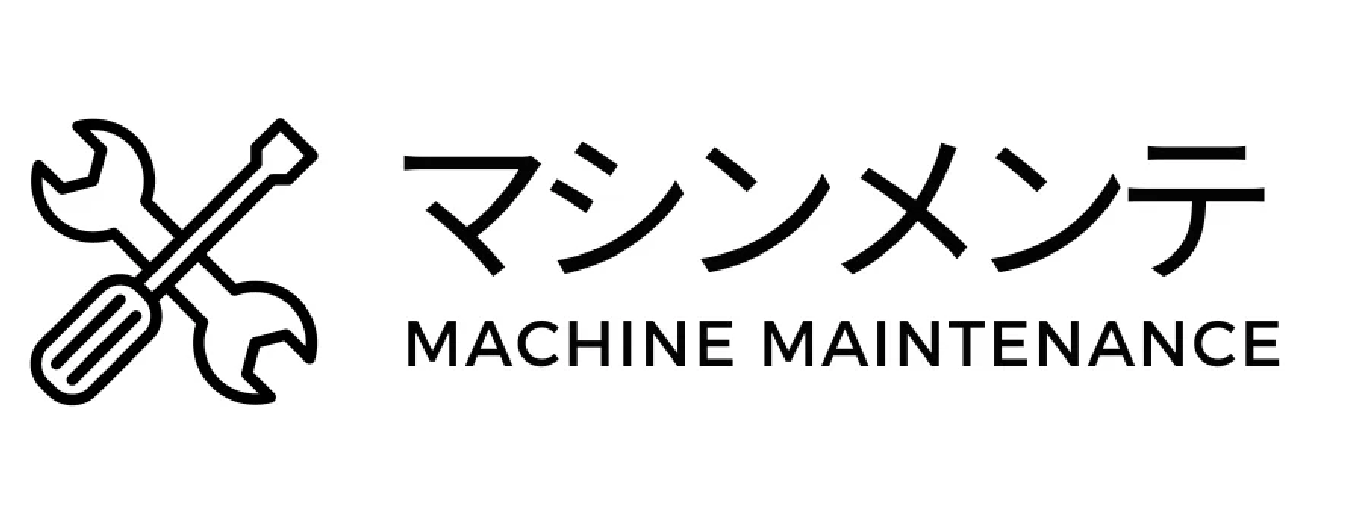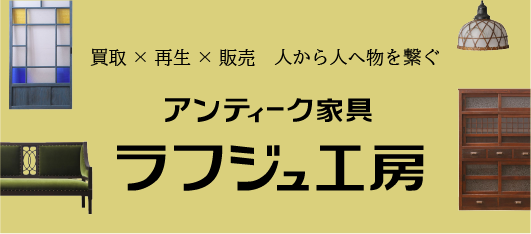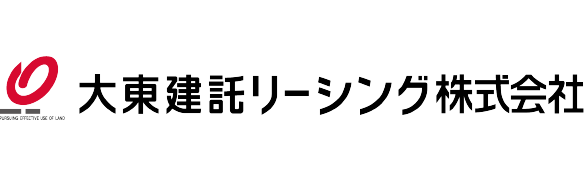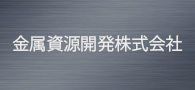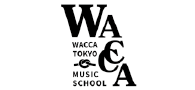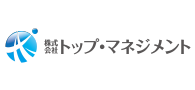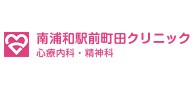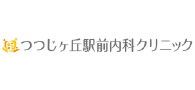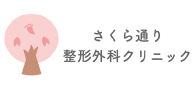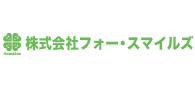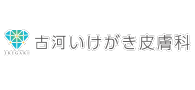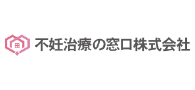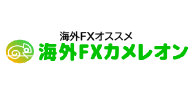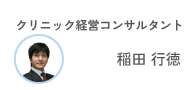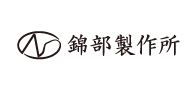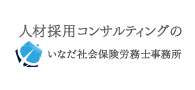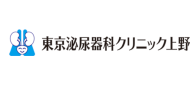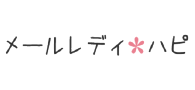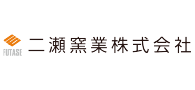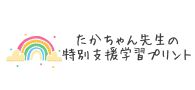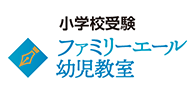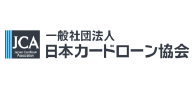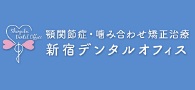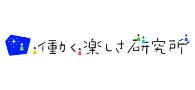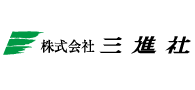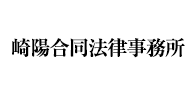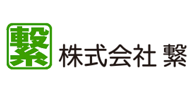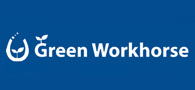企業の社会的責任を学ぶ、そして導入する

企業の社会的責任(corporate social responsibility、略称:CSR)とは、企業が倫理的観点から事業活動を通じて、自主的(ボランタリー)に社会に貢献する責任のことです。
概要
CSRは企業が利益を追求するだけでなく、組織活動が社会へ与える影響に責任をもち、あらゆるステークホルダー(利害関係者:消費者、投資家等、及び社会全体)からの要求に対して適切な意思決定をする責任を指すものです。
CSRは企業経営の根幹において企業の自発的活動(社会的活動)として、企業自らの永続性を実現し、また、持続可能な未来を社会とともに築いていく活動になります。
企業の行動は利益追求だけでなく多岐にわたるため、企業市民という考え方もCSRの一環として主張されているのです。
CSRの多様性
CSRは地域、国家、企業により発展の仕方が異なることをご存知ですか。
ヨーロッパ
ヨーロッパにおいては、消費者に対するイメージ向上を狙い、顧客誘引力を上げようという考えによって行われる活動はCSRとして評価されていません。
ヨーロッパにおけるCSRとは社会的な存在としての企業が、企業の存続に必要不可欠な社会の持続的発展に対して必要なコストを払い、未来に対する投資として必要な活動を行うことと定義されています。
時として、アメリカ型の市場中心主義へのアンチテーゼとして語られることもありますが、EUが主導的に様々な基準を整備していることや、環境、労働等に対する市民の意識が高いこともあり、総じて企業としてCSRに対する取り組みは包括的であり、企業活動の根幹として根付いております。
アメリカ
アメリカでは、1990年代の後半から、企業は利益を追求するだけでなく、社会環境への配慮、コミュニティーへの貢献などが求められております。
2000年代になると企業改革・更生法ともいえるサーベンス・オックスレー法が成立されていくなど、企業に対する社会的責任を法律で定めていくというような法的整備・拘束等が進められております。
日本
日本では1970年代から企業の社会的責任ということばが使われております。
しかしながら、一般に日本企業がCSRに期待するものは、「企業の持続的発展」であり、そのため、しばしば企業の社会的責任は企業の社会的貢献や企業イメージの向上を図る慈善活動のように考えられ、このため企業収益を実現した後の活動のみを指すものと誤解されてきました。
また、企業活動における利益実現が主の目標でCSRは従と考えている企業経営者はいまだ多く、利益幅の小さな企業におけるCSRの活動の取り組みはあまり進んでおりません。
経済団体などではCSRの普及に努めており、一定の成果をみせているものの特に日本の企業において圧倒的に多い中小企業の意識の変化には時間がかかると思われるが、否応でも取り組まざるを得ない課題となっているのです。
CSRの導入
統計省の調査分析で、今後10年後に生き残れる企業が6.4%という驚きの数値が公開された。これからどの企業も対応策に追われていくことと考えます。
そんな中、残る企業と残らない企業が別れていきます。
自主的に社会に対して貢献をしているところが、地域コロニーに中で、生き残っていく考え方もございます。
私たちの想い
“企業が日本の子ども達に目を向けてほしい”
“児童養護施設を卒園する子ども達の生活を支えてほしい”
“夢を叶えられる環境にしてほしい”
“就労支援をしてほしい”
“生活保護を受ける生活ではなく、支えがあり自分が本当にやりたことができる環境にしてほしい”
中小企業の皆様、CSRを始めましょう!
こちらからCSRを始められます。
<個人の方からのご寄付はこちらの画像をクリックしてください>
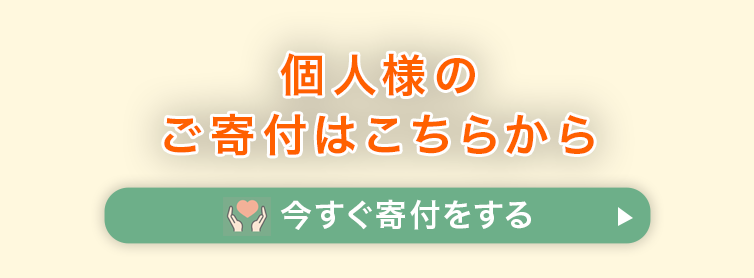
<企業スポンサーとしてのご寄付はこちらの画像をクリックしてください>
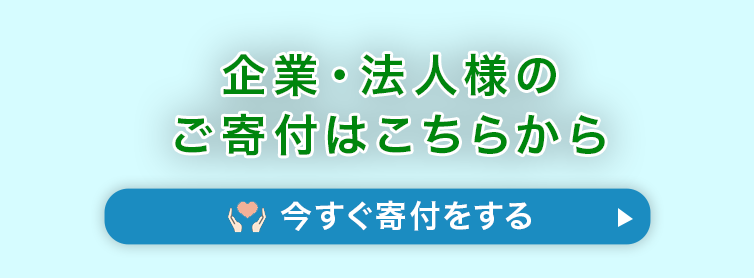
オレンジの羽根募金
児童養護施設の子どもが安心できる社会づくりへ
「オレンジの羽根運動」は、児童養護施設の現場職員が発足した社会活動です。
入所中の子どもたち、卒園する子どもたちにとってより良い社会で生活するために児童養護施設を正しく知っていただき、
共に支える大人の輪をつくることが目的です。
そんな想いで、私たちはこの活動を行なっています。
多くのみなさまへ活動を周知されるご協力をよろしくおねがいします。
▶︎WEBページはこちら
【FM世田谷/放送中】はなわと岩崎ひろみの ON AIR もっち〜ラジオ

お笑いタレント“はなわ”と女優の“岩崎ひろみ” がお届けする『ON AIR もっち~ラジオ』♪” 子どもたちの“ワクワク♪”を、もっと大きく膨らまそう ”をテーマに、“はなわ”と“岩崎ひろみ”が、子育て経験も交えて面白おかしく元気にお届けします!
〈放送日時)毎週日曜日/11:00~11:15
〈パーソナリティ〉はなわ 岩崎ひろみ
▶︎WEBページはこちら
【公開中】Youtubeチャンネル

日本児童養護施設財団のYoutubeチャンネルにて、『もっち〜とあっき〜が行く施設長インタビュー』『応援メッセージ』『ON AIR もっち〜ラジオのアーカイブ』『寄付サイト』のPVが公開中です。チャンネル登録して頂けますと幸いです。
▶︎チャンネルはこちら
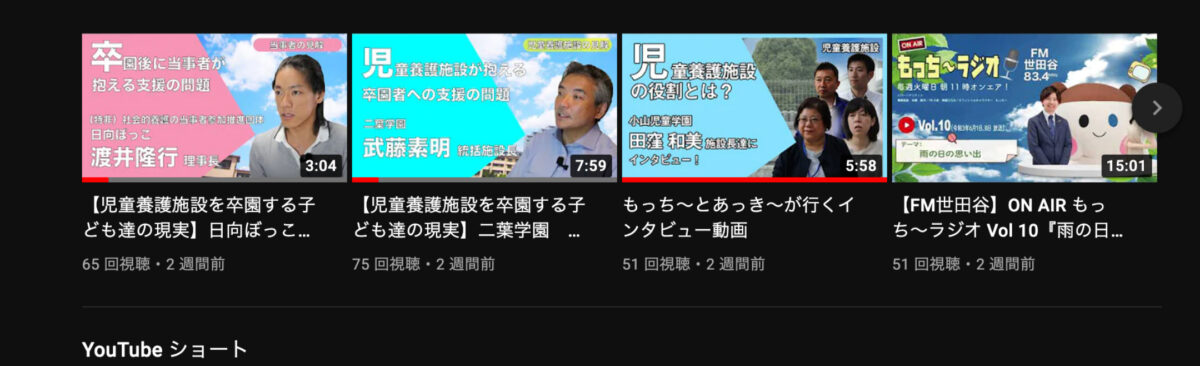
【無料掲載】卒園生対象 企業求人サイト
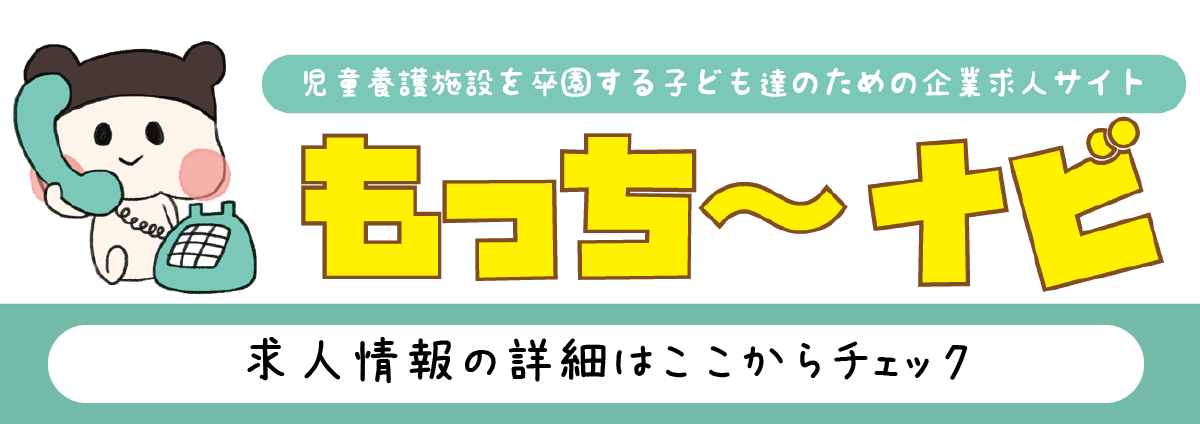 もっち〜ナビは就職を希望する子どもたちの選択肢が広がるように願いを込めて運営している児童養護施設専門の求人サイトです。施設で暮らす若さ溢れる子どもたちを積極的に採用したい企業のみが求人掲載をしているので、これから施設を退所する高校生や一度施設を退所した卒園児が再就職を目指す場合に活用してください。求人情報にある企業の窓口にご連絡をしていただけますと、求人担当から案内を受けることができます。この事業は営利活動ではないため、掲載課金、採用課金、応募課金、オプション課金は一切しておりません。掲載したい企業も随時募集しております。
もっち〜ナビは就職を希望する子どもたちの選択肢が広がるように願いを込めて運営している児童養護施設専門の求人サイトです。施設で暮らす若さ溢れる子どもたちを積極的に採用したい企業のみが求人掲載をしているので、これから施設を退所する高校生や一度施設を退所した卒園児が再就職を目指す場合に活用してください。求人情報にある企業の窓口にご連絡をしていただけますと、求人担当から案内を受けることができます。この事業は営利活動ではないため、掲載課金、採用課金、応募課金、オプション課金は一切しておりません。掲載したい企業も随時募集しております。
▶︎WEBページはこちら
【開館中】日本子ども未来展 オンライン美術館
 日本子ども未来展は、児童養護施設の子どもたちの豊かな成長を願うと共に、子どもたちが描く絵画を通して日々の生活だけでなく、子どもたちがそれぞれ持つ「夢」や「希望」を自由に表現する事で自分たちの将来について考える「きっかけ」を持ってもらうことを目的に実施しております。是非ご入館してみてください。子どもたちの素敵な感性や表現力の高さを垣間見れるので手を差し伸べたくなると思います。
日本子ども未来展は、児童養護施設の子どもたちの豊かな成長を願うと共に、子どもたちが描く絵画を通して日々の生活だけでなく、子どもたちがそれぞれ持つ「夢」や「希望」を自由に表現する事で自分たちの将来について考える「きっかけ」を持ってもらうことを目的に実施しております。是非ご入館してみてください。子どもたちの素敵な感性や表現力の高さを垣間見れるので手を差し伸べたくなると思います。
▶︎WEBページはこちら
【寄付】あしながサンタ
 2019年8月に全国の児童養護施設(607施設)へ、クリスマスに関してのアンケート調査を実施しました。アンケート調査により、1施設あたりの子ども1人に対してのクリスマスプレゼント代の平均予算(約3000円)がわかりました。そこで分かったのが、どの施設も子どもたちが施設生活を送る上で、不自由がない生活を送らせるために、クリスマスの予算を、習い事、衣服費、小遣い、ユニット旅費などに、適切に振り分けられていることがわかりました。ここに私たちがサポートできることがあると考えました。
2019年8月に全国の児童養護施設(607施設)へ、クリスマスに関してのアンケート調査を実施しました。アンケート調査により、1施設あたりの子ども1人に対してのクリスマスプレゼント代の平均予算(約3000円)がわかりました。そこで分かったのが、どの施設も子どもたちが施設生活を送る上で、不自由がない生活を送らせるために、クリスマスの予算を、習い事、衣服費、小遣い、ユニット旅費などに、適切に振り分けられていることがわかりました。ここに私たちがサポートできることがあると考えました。
▶︎WEBページはこちら