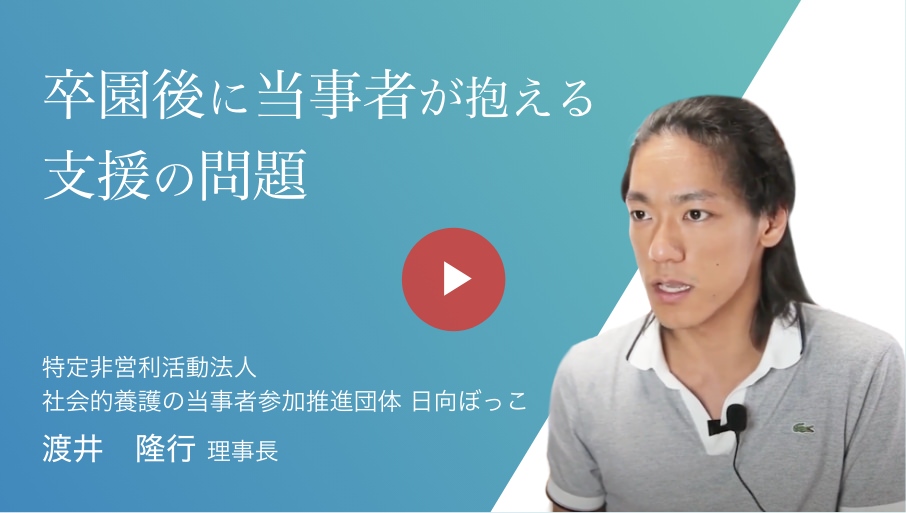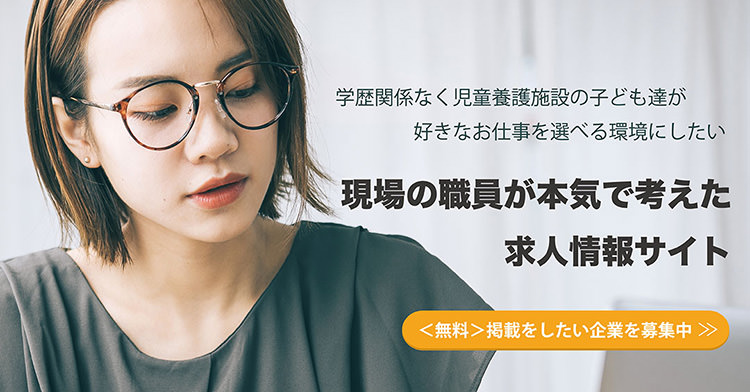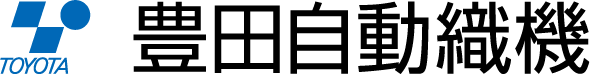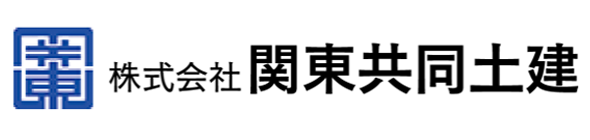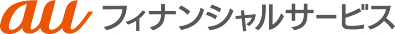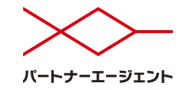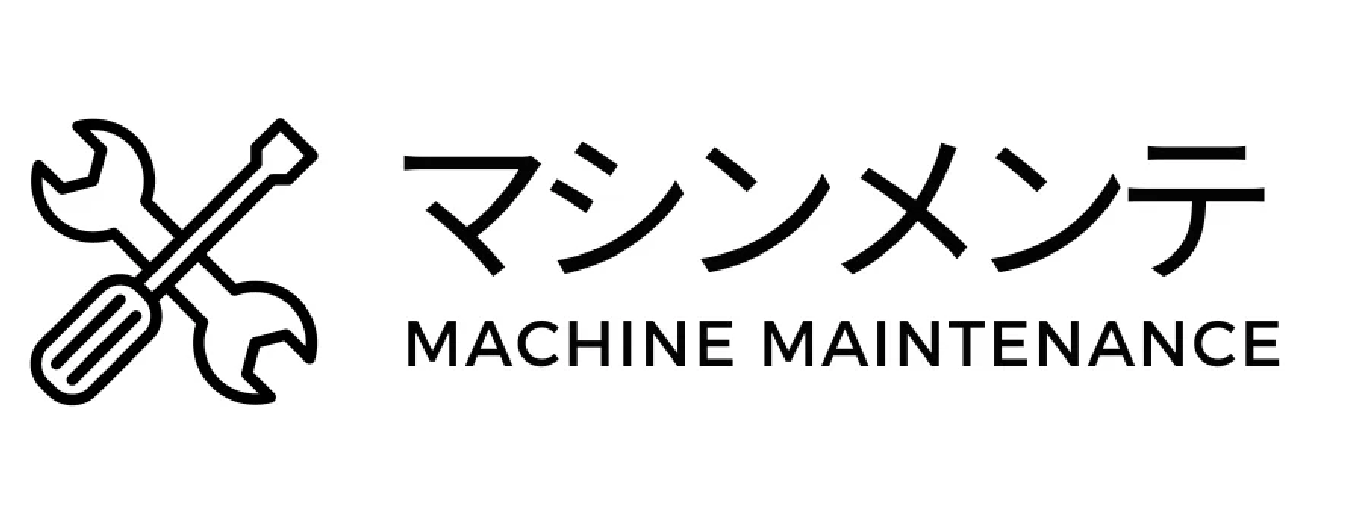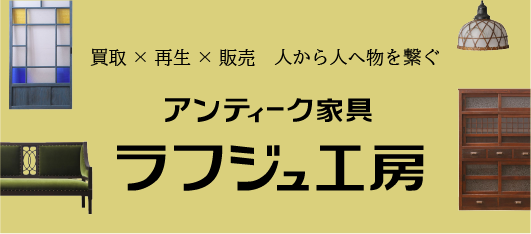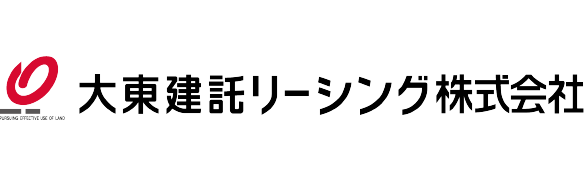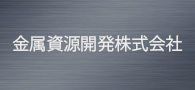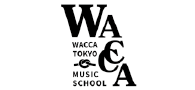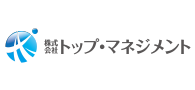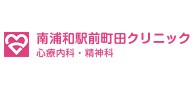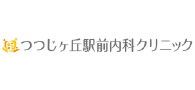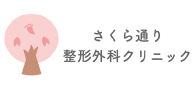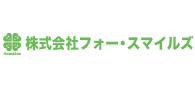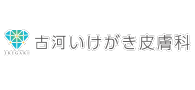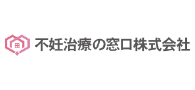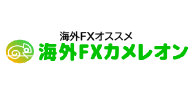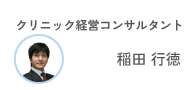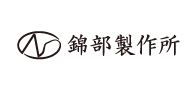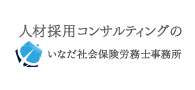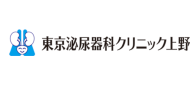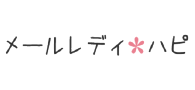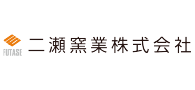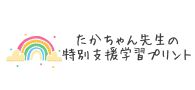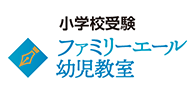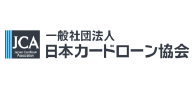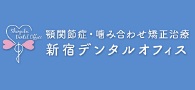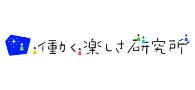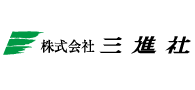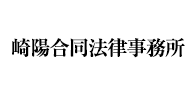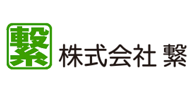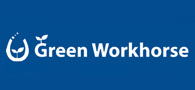救世軍機恵子寮さん インタビュー 第3弾
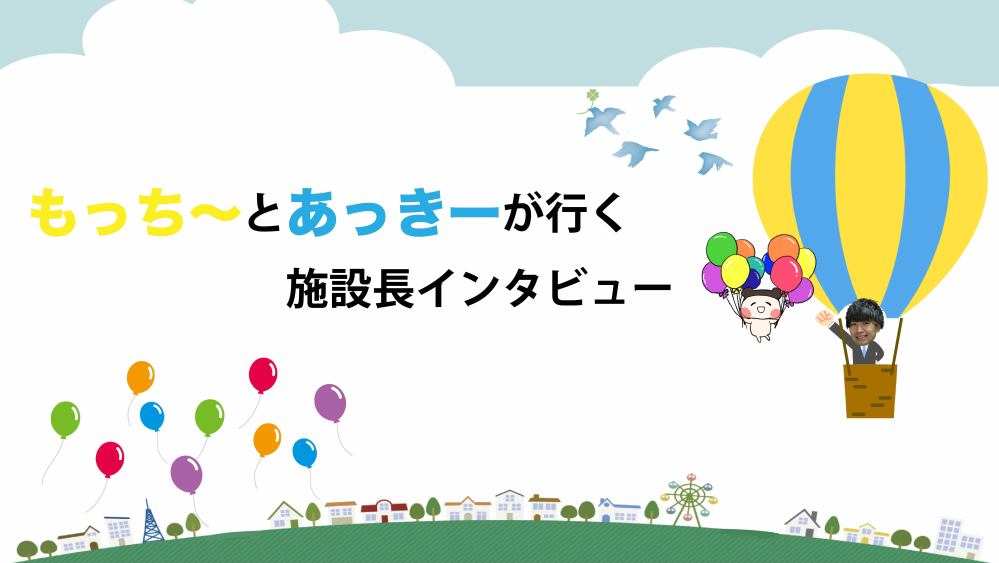
以前、ご紹介させていただいております「もっち~」と「あっき~」が行く施設長インタビュー第3弾!そのインタビュー記事がまとまりましたので報告させていただきます!
「もっち~」と「あっき~」が行く施設長インタビューとは?
「もっち~」と「あっき~」が行く施設長インタビューとは全国児童養護施設総合寄付サイトの マスコットキャラクター「もっち〜」と事務局長である本郷(あっき〜)が全国の児童養護施設の施設長の元に児童養護施設に関して現場の生の声を聞きに行くインタビュー活動となっております。
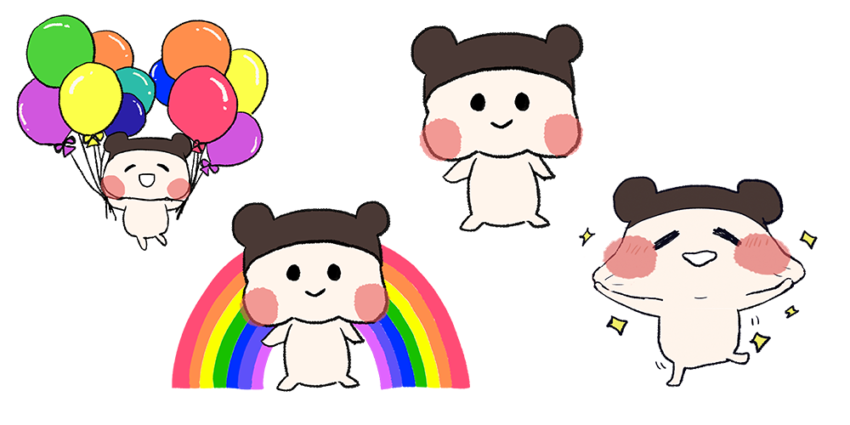
↑全国児童養護施設総合寄付サイトマスコットキャラクター「もっち〜」
※もっち〜についての詳細はこちら
インタビュー
今回は東京都の杉並区にある児童養護施救世軍世光寮の塩田副施設長様にお聞きした際のインタビュー記事が完成したのでこちらで報告させていただきたいと思います。


インタビュー内容
施設についてのご紹介をお願いしますもっち〜
塩田副施設長より:私たちの児童養護施設は、小舎生で定員56名のユニット性です。 分園が3つ、本園が5つのユニットで、全部で8ホームです。 本園は8名以下、7名の定員です。 もう少し小規模化、地域分散化が進めば良いなと考えます。
施設で大切にしてことは、子ども一人ひとりの個別化です。 施設の特徴として、行事などがなく、横割りで集まることも一切しません。 職員から旅行やキャンプの提案がありますが、職員と一対一での関係を心掛けようにしております。 しかし、高校生になると職員と一対一だと恥ずかしい年齢になります。その時は無理には行きません。 此処で、趣味を楽しめるように工夫をしております。 このようなことを続けていたら、ある日突然、子どもの方から「一緒にお墓まいりに行けない?」と尋ねられました。 年齢を重ねることにより、自分自信のルーツを知りたくなるのです。 自分の住んでいた所に、自分の事を知っている人がいるかもしれない、だからこそそこを訪ねたいといった様に、ライフストーリーの素材集めを職員とする子ども達が増えてきたのです。
また施設の行事を皆で行うよりかは、一人ひとりの子ども達の時間を大切にしております。 塾や習い事など地域のコミュニティに出て行く方が、社会的な自我も芽生えた上に友人関係も上手くいきます。 また施設にボランティアを呼ぶ事もほとんどありません。 (目的を持ったボランティア(園芸や散髪)や必要があって塾に行きたいがいけない子の為に家庭教師のようなボラさんを依頼することはたまにありますが) ですので、家庭教師も学習ボランティアでなく、雇う形でやっております。
学校も子ども達にあった学校選びをしていおり、小学校や中学校でも私立を利用している子もいます。 例えば発達障害の子どもで授業中に座ってられないなど、他の子に迷惑をかけてしまう子はすぐに施設の職員が付き添う事を求められたりします。 そのことに関して付き添うのは構いませんが、子どもがなぜ自分だけなのと思っってしまう事や、学校で普通に勉強することができるようになりたい!と思うことが少なからずあります。 そういった子たちの少人数のサポート校は東京では探せばいくつでもあるのです。
しかし現実として、東京都も当然そこにお金を出せません。 学費は年間100万円ほどかかります。 どうにかやりくりして、年間数名の子を小中サポート校に通わせています。
このように、私たちは子どもに合った、学校に通わせる事を大切にしているのです。 個々のニーズを大切に考えることは、職員教育でも強化しております。 施設の中の生活では、お世話は100%職員が行います。 施設を出る時のために、子ども達が中学生になった時から、食器洗い、洗濯物、布団の上げ下ろしなどを自分で行わせる施設もあります。 私たちは違います。全て職員が行い、入所中の子ども達に本来の子どもらしさを取り戻すきっかけに力を入れています。
情緒面を豊かにしそこからの社会自律を目標にしています。 ですので、子ども達が自分からやりたい!と思うまでは、職員が行うことが大切なのです。 もちろん施設を卒園する数ヶ月前には、使い方をレクチャー致しますよ。 気持ち良いの良い環境で、その環境をキープしたいから掃除や洗濯等をする気持ちを大事にしています。 その代わり部屋には誰も入りませんが、汚くしていれば職員が入り綺麗にします。施設全体のルールはなく、子ども達、一人ひとりとの約束といった形を取っています。
児童養護施設について教えて欲しいもっち〜
塩田副施設長より:児童養護施設は児童福祉が根拠にある施設です。 親が居ても家庭で生活できない子ども達がとても多く、約6割が虐待によって入所するケースが多いです。 実態に親が精神疾患であれば当然、生活機能が失われていく中で育てられていくわけですからネグレクトも起きています。 今はDV被害も心的虐待の中にカテゴライズされています。 何らかの形で不適切な養育を受けてきた子が入所してくる施設に形を変えております。
社会的養護の現状と課題について教えて欲しいもっち〜
塩田副施設長より:現状は虐待相談数が約13万あります。 同じだけの相談数が子ども家庭支援センターや児童相談所にあるとすれば年間26〜27万件の相談数があります。 それが新規の相談数ですので、継続ケースだともっと多いです。 その中で社会的な受け皿が4万5千、里親が圧倒的に少なく期間もない中で必死に介入しています。 しかし枠が少ないこともあり、本当に危ないケースばかり入ってきていて年間45,000のうちの4,500しか空きがないので本当に足りない状況です。 今後、日本は施設養育から里親養育を増やして行く方針ですが、里親の数は圧倒的に少ないですし、里親をサポートする機関も必要です。 里親との関係が不調で帰ってくる子ども達や、なかなか里親に結びつかない子ども達を見ると重要な問題だと感じてしまいます。
巣立ち後の子ども達の状況について教えて欲しいもっち〜
塩田副施設長より:心が育っていない中で巣立っていた子ども達は、心が折れてしまいます。 また決められたルールの中で生活していた子は、一人で生活した時にいきなり自由になってしまい、どうしたら良いのかわかりません。 そのために、一気に羽を伸ばしてしまうか、本当に指示がないと動けず引きこもりになっていってしまうことも多く、会社も途中で行けなくなってしまったりします。 そんなこともあり、最近では、心を育ててから巣立たせるように心掛けております。施設において卒業し、しばらく自立期間をおいてから退所にするようにしてから、上手くやっていけるようになった子が増えました。 ただそれでも失敗して戻ってくる子や、助けを求めてくる子は後を絶ちません。 子どもが十分に成長することを考えるなら、最低でも25、6歳まで手を差し伸べてあげなければならないのです。
職員の声を形にした寄付サイトについて一言お願いしますもっち〜
塩田副施設長より:子どもの現状を知っている人たちが立ち上げていますので、本当に必要なサポートを知っております。敬意を表します。ありがとうございます。
支援をしていただける企業、寄付者へ一言お願いしますもっち〜
塩田副施設長より:巣立つ子ども達のために、物資より寄付が大切です。 理解していただきご寄付をお願いします。

インタビューを通して
インタビューを通し直接、施設長様に話を聞くことで今まで以上に色々なことを学ばせていただける機会となりました。これから施設を巣立つ子ども達には、まだまだ支援が行き渡ってるとは言えません。現物での支援はありがたい反面、有り余ってしまっている現状なのも事実なのです。施設を出て社会で1人で行きていく子ども達には現物の物以上にお金がの支援が必要です。だからこそ私たち現場職員は立ち上がり活動しています。私たちの支援の仕方は施設、現場職員の私たちだからこそできる事です。これからも一歩ずつ着実に頑張り現場の声を更に届けていきたいと思います。そして施設を卒園する子ども達の夢や希望を叶えるキッカケを作って行きたいと考えています。どうかご寄付のほど、宜しくお願い申し上げます。
今回訪問した救世軍世光寮さんのホームページはこちら
<個人の方からのご寄付はこちらの画像をクリックしてください>
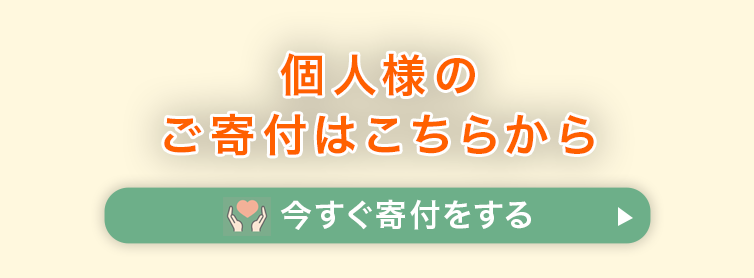
<企業スポンサーとしてのご寄付はこちらの画像をクリックしてください>
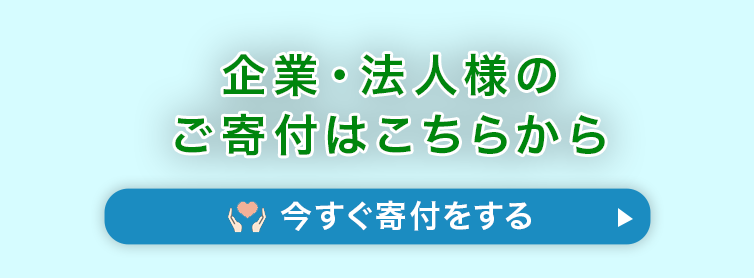
オレンジの羽根募金
児童養護施設の子どもが安心できる社会づくりへ
「オレンジの羽根運動」は、児童養護施設の現場職員が発足した社会活動です。
入所中の子どもたち、卒園する子どもたちにとってより良い社会で生活するために児童養護施設を正しく知っていただき、
共に支える大人の輪をつくることが目的です。
そんな想いで、私たちはこの活動を行なっています。
多くのみなさまへ活動を周知されるご協力をよろしくおねがいします。
▶︎WEBページはこちら
【FM世田谷/放送中】はなわと岩崎ひろみの ON AIR もっち〜ラジオ

お笑いタレント“はなわ”と女優の“岩崎ひろみ” がお届けする『ON AIR もっち~ラジオ』♪” 子どもたちの“ワクワク♪”を、もっと大きく膨らまそう ”をテーマに、“はなわ”と“岩崎ひろみ”が、子育て経験も交えて面白おかしく元気にお届けします!
〈放送日時)毎週日曜日/11:00~11:15
〈パーソナリティ〉はなわ 岩崎ひろみ
▶︎WEBページはこちら
【公開中】Youtubeチャンネル

日本児童養護施設財団のYoutubeチャンネルにて、『もっち〜とあっき〜が行く施設長インタビュー』『応援メッセージ』『ON AIR もっち〜ラジオのアーカイブ』『寄付サイト』のPVが公開中です。チャンネル登録して頂けますと幸いです。
▶︎チャンネルはこちら
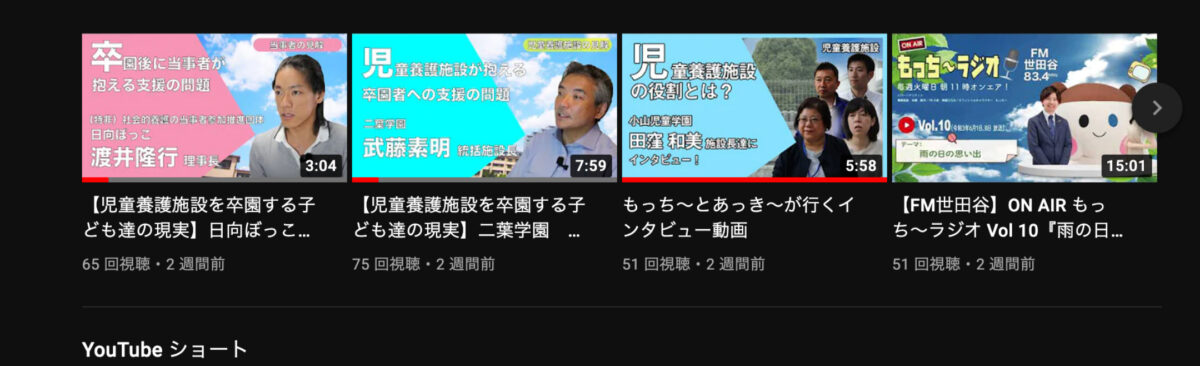
【無料掲載】卒園生対象 企業求人サイト
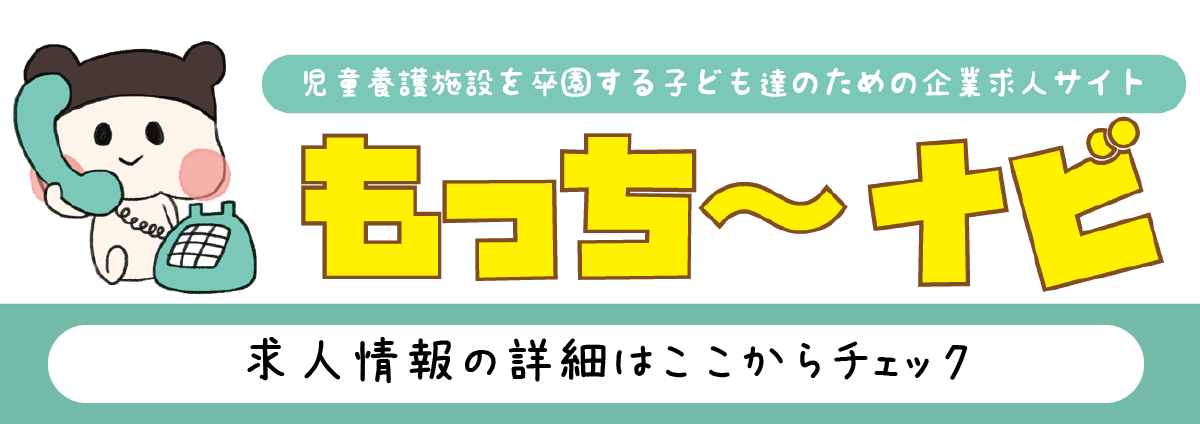 もっち〜ナビは就職を希望する子どもたちの選択肢が広がるように願いを込めて運営している児童養護施設専門の求人サイトです。施設で暮らす若さ溢れる子どもたちを積極的に採用したい企業のみが求人掲載をしているので、これから施設を退所する高校生や一度施設を退所した卒園児が再就職を目指す場合に活用してください。求人情報にある企業の窓口にご連絡をしていただけますと、求人担当から案内を受けることができます。この事業は営利活動ではないため、掲載課金、採用課金、応募課金、オプション課金は一切しておりません。掲載したい企業も随時募集しております。
もっち〜ナビは就職を希望する子どもたちの選択肢が広がるように願いを込めて運営している児童養護施設専門の求人サイトです。施設で暮らす若さ溢れる子どもたちを積極的に採用したい企業のみが求人掲載をしているので、これから施設を退所する高校生や一度施設を退所した卒園児が再就職を目指す場合に活用してください。求人情報にある企業の窓口にご連絡をしていただけますと、求人担当から案内を受けることができます。この事業は営利活動ではないため、掲載課金、採用課金、応募課金、オプション課金は一切しておりません。掲載したい企業も随時募集しております。
▶︎WEBページはこちら
【開館中】日本子ども未来展 オンライン美術館
 日本子ども未来展は、児童養護施設の子どもたちの豊かな成長を願うと共に、子どもたちが描く絵画を通して日々の生活だけでなく、子どもたちがそれぞれ持つ「夢」や「希望」を自由に表現する事で自分たちの将来について考える「きっかけ」を持ってもらうことを目的に実施しております。是非ご入館してみてください。子どもたちの素敵な感性や表現力の高さを垣間見れるので手を差し伸べたくなると思います。
日本子ども未来展は、児童養護施設の子どもたちの豊かな成長を願うと共に、子どもたちが描く絵画を通して日々の生活だけでなく、子どもたちがそれぞれ持つ「夢」や「希望」を自由に表現する事で自分たちの将来について考える「きっかけ」を持ってもらうことを目的に実施しております。是非ご入館してみてください。子どもたちの素敵な感性や表現力の高さを垣間見れるので手を差し伸べたくなると思います。
▶︎WEBページはこちら
【寄付】あしながサンタ
 2019年8月に全国の児童養護施設(607施設)へ、クリスマスに関してのアンケート調査を実施しました。アンケート調査により、1施設あたりの子ども1人に対してのクリスマスプレゼント代の平均予算(約3000円)がわかりました。そこで分かったのが、どの施設も子どもたちが施設生活を送る上で、不自由がない生活を送らせるために、クリスマスの予算を、習い事、衣服費、小遣い、ユニット旅費などに、適切に振り分けられていることがわかりました。ここに私たちがサポートできることがあると考えました。
2019年8月に全国の児童養護施設(607施設)へ、クリスマスに関してのアンケート調査を実施しました。アンケート調査により、1施設あたりの子ども1人に対してのクリスマスプレゼント代の平均予算(約3000円)がわかりました。そこで分かったのが、どの施設も子どもたちが施設生活を送る上で、不自由がない生活を送らせるために、クリスマスの予算を、習い事、衣服費、小遣い、ユニット旅費などに、適切に振り分けられていることがわかりました。ここに私たちがサポートできることがあると考えました。
▶︎WEBページはこちら